リベートとは
リベート(rebate)とは、英語で手数料・謝礼・賄賂を意味します。卸売業や小売業の取引高に応じて、メーカーがその仕入代金の一部を払い戻すことを指します。
リベートの目的をわかりやすくいえば、メーカーの販売促進です。
商品の販売や請負などで競争が激しくなると、メーカーは契約金額の一定歩合を流通業者に戻すことを条件として、その契約を成立させます。つまり、謝礼を渡すことで自社の商品を取り扱ってくれる取引先や取引量を増やしてもらう目的があります。
リベートはあらかじめ取引金額や商品の代金を割引するのではなく、支払金額の一部を払い戻すことが特徴です。取引価格が変動する可能性があることから、取引価格の算定に関する論点となります。
収益認識基準の適用について
収益認識に関する会計基準においては、顧客に支払われる対価は、顧客から受領する別個の財またはサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格から減額するとされています。
つまり、将来リベートを支払うと予想される部分については、収益を認識せず返金負債(負債)勘定を計上します。
顧客に支払われる対価は、企業が顧客(あるいは顧客から企業の財又はサービスを購入する他の当事者)に対して支払う又は支払うと見込まれる現金の額や、顧客が企業(あるいは顧客から企業の財又はサービスを購入する他の当事者)に対する債務額に充当できるもの(例えば、クーポン)の額を含む。顧客に支払われる対価は、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格から減額する。
引用:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」
リベートの例題
当社は製品を外部のX社へ販売しており、販売条件の契約内容は下記の通りである。
- 製品の1個あたりの販売価格は10,000円である。
- X社への製品の年間販売個数が300個に達した場合は1個あたり500円、1,000個に到達した場合は1個あたり1,000円のリベートを当社がX社に支払う。
- 当期における製品のX社への年間販売個数は600個と予測している。
- 当期の第一四半期において、X社へ製品を140個販売した。
- 当社は、変動対価に関する不確実性が事後的に解消される時点までに、計上される収益の額の著しい減額が発生しない可能性が極めて高いと判断した。
解答・解説
値引きされると見込まれる金額については、収益を認識せず 返金負債(負債)勘定を計上します。そのため、収益の額は、値引きされると見込まれる対価の額を除いて算定します。
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
| 現 金 預 金 | 1,400,000 | 売 上 返 金 負 債 | 1,330,000 70,000 |
この時、第一四半期において140個販売しており、年間で560個(140個×4期分)を販売することが予想されます。
そのため、販売個数は「300個 ≦ 560個 ≦ 1,000個」となり、値引額は1個あたり500円と見込んで返金負債を算定します。
現金預金:10,000円×140個(販売個数)= 1,400,000
売 上:(10,000円ー500円(リベート見込))×140個 =1,330,000
返金負債:500円(リベート見込)×140個 = 70,000
値引額の見積もりを修正した場合
(追加)第二四半期におけるX社への製品の販売数量は400個であった。第二四半期における仕訳を示しなさい。
第二四半期においては、累計で540個(140個+400個)販売しており、年間で1,080個(540個×2期)となり、1,000個以上販売することが可能であると見込まれます。
そのため、製品1あたりの値引を1,000円として返金負債を算定します。
| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
| 現 金 預 金 | 4,000,000 | 売 上 返 金 負 債 | 3,530,000 470,000 |
現金預金:10,000円×400個(販売個数)= 4,000,000
売 上:貸借差額
返金負債:1,000円 × 540個 ー70,000円(第一四半期の返金負債))= 470,000
540個分の値引額は、540,000円(540個×1,000円)となります。ただし、前期(第一四半期)に返金負債70,000円を計上しているので、第二四半期においては470,000円(540,000ー70,000)を返金負債として計上します。
取引価格の事後的な変動については、契約における取引開始日後の独立販売価格の変動を考慮せず、契約における取引開始日と同じ基礎により契約における履行義務に配分する。取引価格の事後的な変動のうち、既に充足した履行義務に配分された額については、取引価格が変動した期の収益の額を修正する(適用指針[設例 13])。
引用:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」
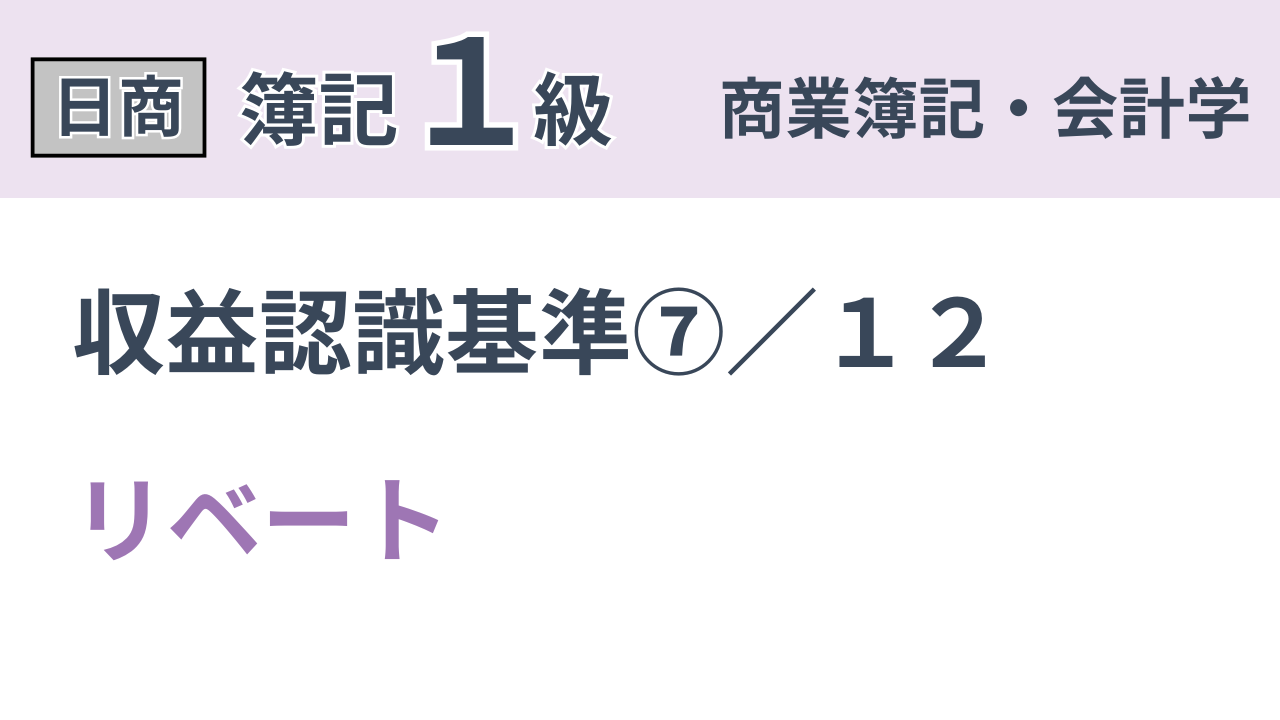
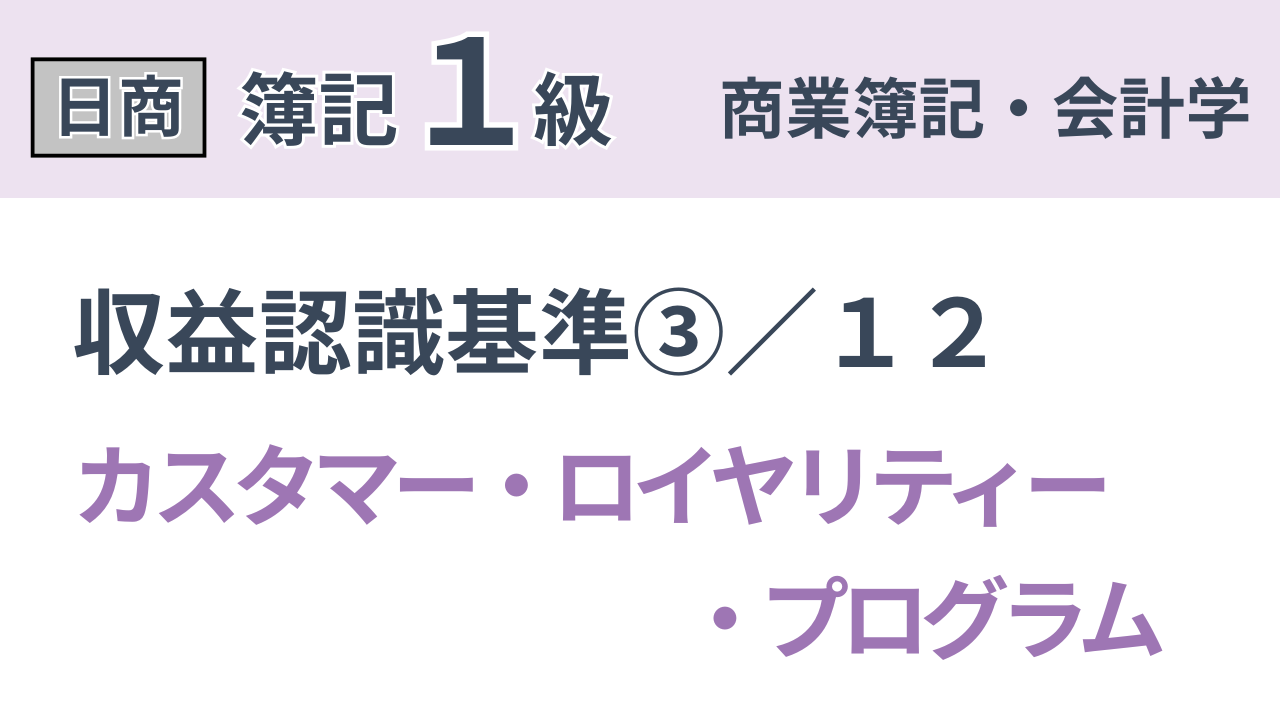
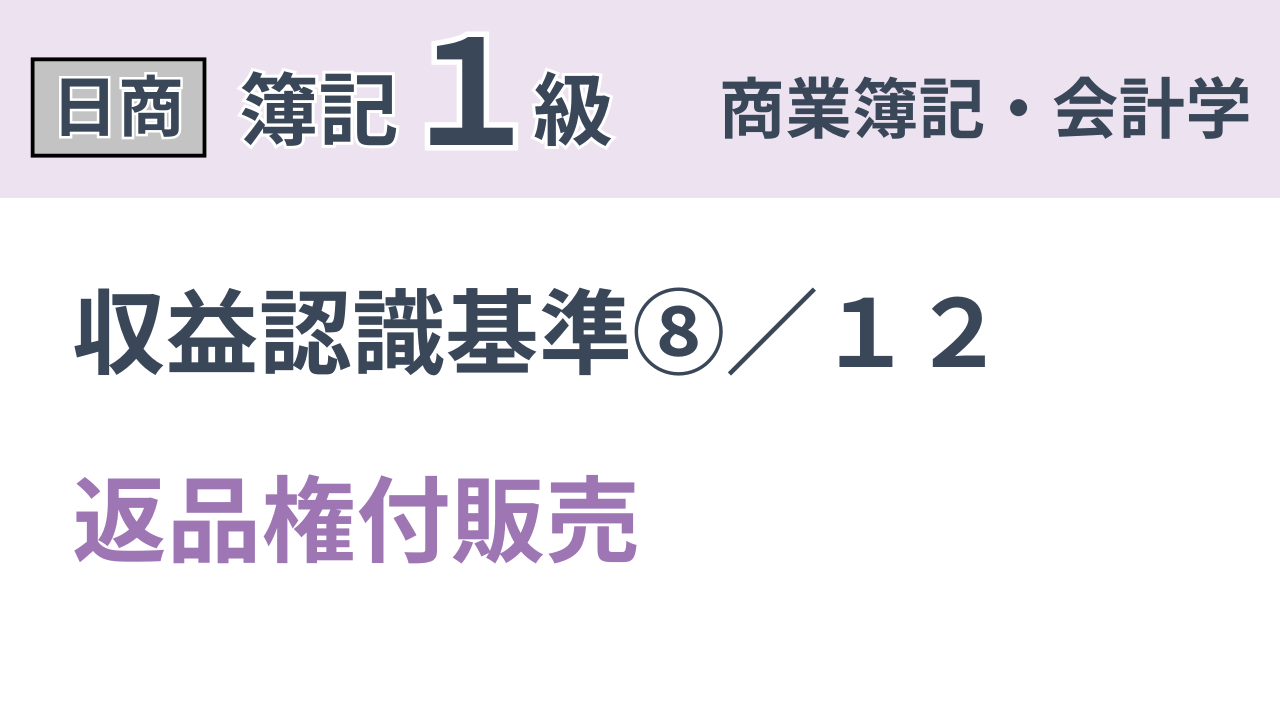
コメント