収益認識基準とは?
収益認識基準(収益認識に関する会計基準)とは、「顧客との契約から生じた収益(売上)を、いつ、いくらで計上するか」を定めた会計基準のことです。
適用対象は、公認会計士の会計監査を受ける会社、つまり会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)および上場企業です。
上場企業が適用対象となることから、将来上場することを検討しているIPO準備企業においても、収益認識基準を適用する必要があります。
収益認識基準導入の背景
日本の企業会計における収益認識の会計基準は、以下のように定められています。
売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。
引用:企業会計基準委員会「企業会計原則」
このように「実現主義」による考え方が原則として示されていたものの、収益認識に関する包括的な会計基準は定められていませんでした。そのため、会社は実現主義である「出荷基準」「引渡基準」「検収基準」の中から自社に適した計上方法を選択して売上高を計上していました。
それにより会社ごとに収益認識のタイミングが異なることになり、作成した財務諸表の正確性や類似企業との比較可能性の観点で問題と捉えられていました。
このような状況を解消すべく、企業会計基準委員会は、2018年3月に収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」を公表したのです。
会計基準の適用範囲
収益認識基準は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理に適用されます。
ただし、以下7つの取引は、収益認識基準以外の会計基準が適用されているため、例外的に収益認識基準の適用対象外となります。
本会計基準は、次の(1)から(7)を除き、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用される。
- 金融商品会計基準の範囲に含まれる金融商品に係る取引
- リース会計基準の範囲に含まれるリース取引
- 保険法における定義を満たす保険契約
- 顧客又は潜在的な顧客への販売を容易にするために行われる同業他社との商品又は製品の交換取引
- 金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料
- 不動産流動化実務指針の対象となる不動産の譲渡
- 資金決済法における定義を満たす暗号資産及び金商業等府令における定義を満たす電子記録移転有価証券表示権利等に関連する取引
引用:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」
会計処理の基本となる原則
収益認識基準では、基本となる原則について以下のように示しています。
本会計基準の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することである。
引用:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」
「財又はサービスが顧客へ移転」に着目して収益を認識するため、企業側からすると、顧客に財又はサービスの支配が移転した時点で履行義務が充足されることになります。
「企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益を計上する」とあるため、財又はサービスを顧客に移転したことで得られる対価の額をもって、収益を認識するということになります。
収益認識基準「5つのステップ」
収益を認識するための手順として、次の5つのステップを検討します。
- 契約の識別(ステップ1)
- 履行義務の識別(ステップ2)
- 取引価格の算定(ステップ3)
- 取引価格の配分(ステップ4)
- 履行義務の充足(ステップ5)
引用:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」
自社製品・サービスの契約ごとに、上記5つのステップを進めることで、収益計上に必要な単位(何を)・金額(いくらで)・計上時期(いつ)を決定します。
ステップ1「契約の識別」
取引が収益認識基準の適用範囲である「顧客との契約」に該当するかを確認します。
契約の識別については、5つの要件が示されています。
- 当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること
- 移転される財又はサービスに関する各当事者の権利を識別できること
- 移転される財又はサービスの支払条件を識別できること
- 契約に経済的実質があること(すなわち、契約の結果として、企業の将来キャッシュ・フローのリスク、時期又は金額が変動すると見込まれること)
- 顧客に移転する財又はサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いこと
引用:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」
原則としては、上記5要件のすべてに該当する場合に顧客との契約と識別され、収益認識基準の適用対象となります。
ステップ2「履行義務の識別」
履行義務とは、顧客との契約において次のいずれかを顧客に移転する約束を言います。
- 別個の財又はサービス(あるいは別個の財又はサービスの束)
- 一連の別個の財又はサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財又はサービス)
引用:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」
履行義務として識別された単位=収益(売上)の単位として計上されるため、履行義務を正しく識別できるかが重要です。
このステップに関連する論点については以下の記事で解説しています。
ステップ3「取引価格の算定」
契約全体における取引価格を算定します。
変動対価、契約における重要な金融要素、現金以外の対価、顧客に支払われる対価を加味して見積もります。
★ 取引価格
財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(第三者のために回収する額を除く)をいう。
ステップ4「取引価格の配分」
1つの契約の中に履行義務が複数存在する場合、各履行義務に対して取引価格を配分します。
配分にあたっては契約において約束した別個の財又はサービスの独立販売価格の比率に基づいて、それぞれの履行義務に取引価格を配分します。独立販売価格を直接観察できない場合には、独立販売価格を見積もって算定します。
★ 独立販売価格
財又はサービスを独立して企業が顧客に販売する場合の価格をいう。
ステップ5「履行義務の充足」
履行義務ごとに、それぞれの履行義務が充足された時点(一時点か、一定期間か)で収益として認識します。
例題
- 当期首にA社は顧客と商品Xの販売と2年間の保守サービスを提供する契約を締結した。
- A社は、当期首に商品Xを顧客に引き渡し、当期首から翌期末まで保守サービスを行うものとする。
- 契約書に記載された対価の額は20,000円である。(商品Xの独立販売価格は16,000円、保守サービスの独立販売価格は4,000円とする。)
- 代金の決済は全て現金で行うものとする。
解答・解説
販売時の仕訳
履行義務の性質にもとづいて、商品Xの販売価格は販売して時点で履行義務を充足するため、売上(収益)勘定を計上します。
一方で、保守サービスの4,000円については一定期間にわたり履行義務を充足するため、当期と翌期の2年間にわたって2,000円ずつ収益を認識します。そのため、販売時点では契約負債(負債)勘定で処理します。
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |
| 現 金 | 20,000 | 売 上 契 約 負 債 | 16,000 4,000 |
当期決算整理仕訳
保守サービスについて、当期に履行義務を充足した部分について収益を認識します。そのため1年分の2,000円(4,000円/2年)を売上(収益)勘定に振り替えます。
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |
| 契 約 負 債 | 2,000 | 売 上 | 2,000 |
翌期決算整理仕訳
保守サービスについて、翌期に履行義務を充足した部分について収益を認識します。そのため、契約負債から売上(収益)勘定に振り替えます。
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |
| 契 約 負 債 | 2,000 | 売 上 | 2,000 |
契約資産と顧客との契約から生じた債権
顧客から対価を受け取る前、又は対価を受け取る期限が到来する前に財又はサービスを顧客に移転した場合は収益を認識し、「契約資産」又は「顧客との契約から生じた債権(資産)」を貸借対照表に計上します。
- 「契約負債」とは、財又はサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものをいう。
- 「顧客との契約から生じた債権」とは、企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)をいう。
引用:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」
すなわち、収益を認識したものの、対価の受け取りが済んでいないものについては「契約資産」か「顧客との契約から生じた債権」を計上します。
「顧客との契約から生じた債権」にある企業の権利のうち無条件のものとは、受け取る期限が到来する前に時の経過以外の条件が存在しない場合をいいます。(売掛金(資産)勘定などが該当する)
一方で、充足した履行義務の対価を顧客に請求する無条件の権利を得る前に、企業が充足しないといけない別の履行義務が存在する場合には契約資産(資産)勘定を計上します。
例題
- 当社は顧客に対して、商品Xと商品Yをそれぞれ4,000円、8,000円で販売する契約を締結している。
- 当期中に商品Xを引き渡し、翌期に商品Yを引き渡した。
- 商品Xの対価の支払いは、商品Yの引き渡しが完了するまで留保され、商品Xと商品Yの両方が顧客ひ引き渡されるまで、対価に対する無条件の権利は有さないものとする。
- 商品Xと商品Yは別個の独立した履行義務であり、それぞれ顧客に引き渡された時点で履行義務が充足する。
解答・解説
商品Xの引き渡し時点(当期)
商品Xを引き渡した時点で、商品Xに対する履行義務を充足するため収益を認識します。ただし、対価の支払いは商品Yの引き渡しが完了するまで保留されるため、契約資産(資産)勘定を計上します。
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |
| 契 約 資 産 | 4,000 | 売 上 | 4,000 |
商品Yの引き渡し時点(翌期)
商品Yを引き渡した時点で、対価に対する無条件の権利を得るため、顧客との契約から生じた債券として売掛金(資産)勘定を計上します。
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |
| 売 掛 金 | 12,000 | 売 上 契 約 資 産 | 8,000 4,000 |
契約負債とは?
財又はサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取る場合には、顧客から対価を受け取ったとき又は対価を受け取る期限が到来したときのいずれか早い時点で、顧客から受け取る対価について契約負債(負債)勘定を計上します。
- 「契約負債」とは、財又はサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものをいう。
引用:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」
例題
- 当社は顧客に対して商品Zを10,000円で販売する契約を締結した。
- 当期に顧客から1000円の対価を現金で受け取った。(引き渡しは翌期に行う)
- 翌期に商品Zを顧客に引き渡した。
解答・解説
対価の受け取り時点(当期)
財又はサービス(本文では「商品Z」)を顧客に移転する前に対価を受け取っているため、契約負債(負債)勘定を用いて処理します。
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |
| 現 金 | 10,000 | 契 約 負 債 | 10,000 |
商品Zの引き渡し時点(翌期)
顧客に財又はサービスを移転して履行義務を充足した時に、契約負債(負債勘定)を売上(収益)勘定に振り替えて収益を認識します。
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |
| 契 約 負 債 | 10,000 | 売 上 | 10,000 |
貸借対照表における表示
収益認識基準には契約資産、契約負債、顧客との契約から生じた債権を適正な科目を持って貸借対照表に表示すると示されています。
- 企業が履行している場合や企業が履行する前に顧客から対価を受け取る場合等、契約のいずれかの当事者が履行している場合等には、企業は、企業の履行と顧客の支払との関係に基づき、契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権を計上する。また、契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権を、適切な科目をもって貸借対照表に表示する(適用指針[設例27])。
引用:企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準」
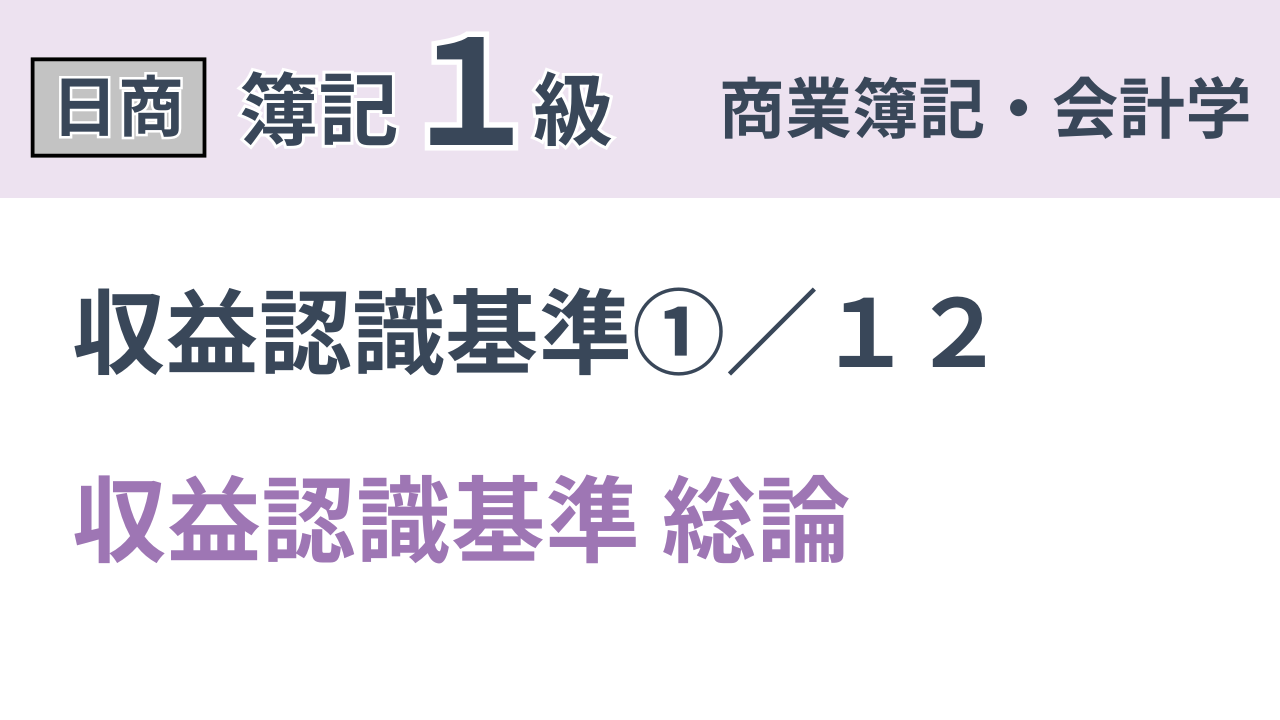
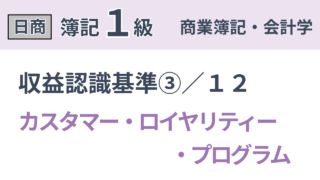
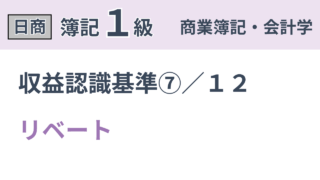
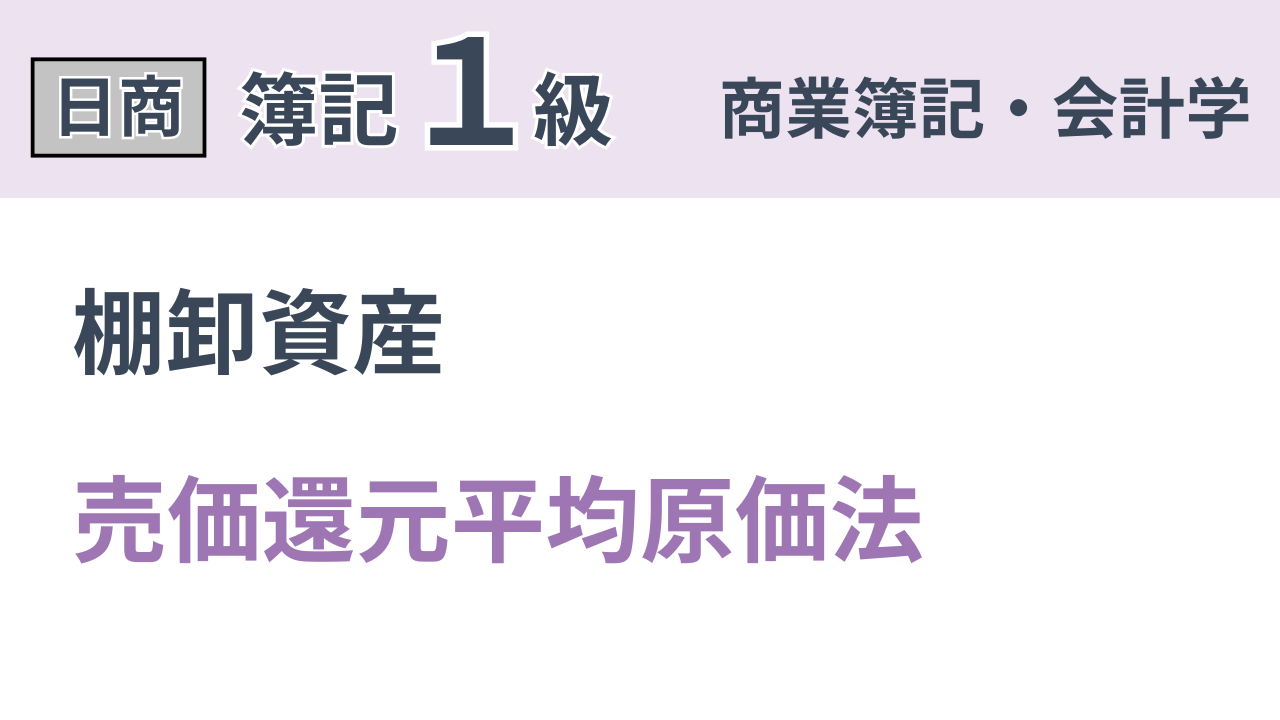
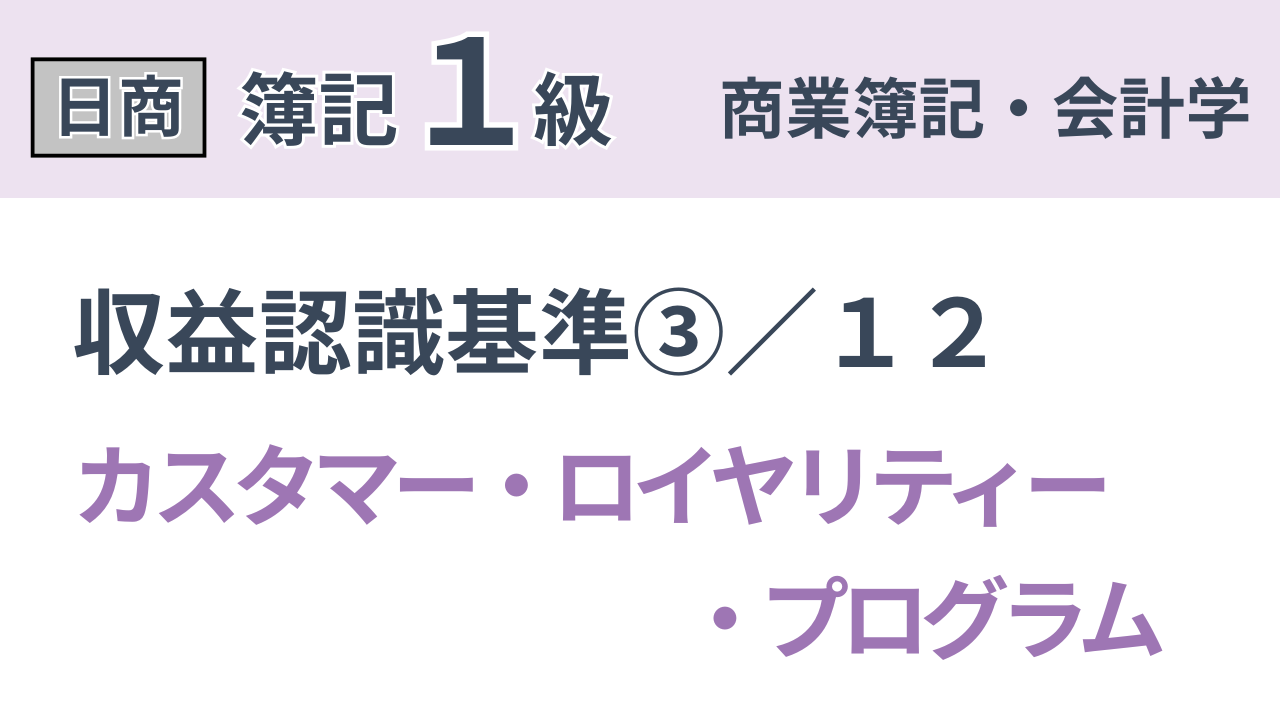
コメント