この記事では、原価企画の概要や目的、さらには原価企画を進める方法についても解説します。
(この記事にはアフィリエイトリンクが含まれます)
原価企画とは?
企業は製品の競争優位の獲得のため、原価企画を実施することがあります。
原価企画とは、製造の企画段階で原価を管理・見積もる仕組みを指すものです。製品開発の源流において、企画の関連部署の総意を集結して原価を作り込むことにより、競争優位の獲得を意図した戦略的な管理手法になります。
原価企画登場の背景
企業を取り巻く経営環境は著しく変化しています。顧客ニーズは多様化し、競争激化の中で顧客志向の製品開発を迫られることで製品ライフサイクルの短縮化をもたらすとともに、生産システムも少品種大量生産から多品種少量生産へと移行してきています。
さらに、生産システムの構築によって、FA化・CIM化の発展へと繋がり、企業の原価管理手法も変革を余儀なくされました。
このような、ライフサイクルの短縮化、FA化・CIM化の発展といった企業環境の変化は、標準原価計算による生産段階での管理機能の重要性を低下させ、原価の大半が製品の企画・設計段階で決定してしまうという状況をもたらしました。
その結果として、原価管理の重点は製品の開発段階へと移行し、その管理手法として原価企画が登場しました。
原価企画の目的と特徴
原価企画の目的は、設計段階において効果的な原価の引き下げを行うことです。ただし、それは単なる原価低減ではなく「マーケット・イン(市場・顧客志向の製品開発)」「開発リードタイムの短縮」「高品質の維持」といった要素をを勘案した上での「原価の作り込み」です。顧客ニーズを反映した高品質な製品をタイムリーに市場に投入することは、企業が競争優位を獲得する上で有効な手段といえます。
企業の目的は利益の獲得であり、原価企画の最終目的も目標利益の確保にあります。企業戦略の根幹である市場戦略は、中長期的な経営計画へと具現化され、原価企画の対象である新製品の企画が行われます。さらに、経営計画は中長期利益計画を経て、具体的な目標利益が設定されます。
このように、原価企画は利益目標達成のための手段であり、その意味では戦略的な利益管理を目的とするものであると言えます。
原価企画の流れ
(1)新製品の企画
顧客ニーズを反映した魅力的な新製品を企画し、製品に必要な機能のおおまかな絞り込みと追加を行います。ここでは、0 Look VE (マーケティングVE)が実施されます。
(2)目標原価の設定と実現
1. 新製品の予定販売価額を設定する。
2. 予定販売価額から目標利益を差し引くことで許容原価を算定する。
3. 新製品の原価見積を行い、成行原価を算定する。
4. 許容原価と成行原価をすり合わせ、成行原価を低減する施策を検討し目標原価を設定する。
5. 目標原価の設定後、その実現に取り組む。ここでは1st Look VE(設計段階で実施)が行われる。
(3)原価管理活動によるフォロー
目標原価をもとに標準原価を設定し、その達成を図ります。具体的には標準原価計算による原価統制(原価維持)、及び原価低減(原価改善)が実施されます。ここでは、2nd Look VE(製造段階や購買段階で実施)が行われます。
(4)販売活動によるフォロー
生産段階において目標利益を達成したとしても、その製品が売れなければ利益は確保できません。そこで、目標利益を確保できる販売量の獲得が必要になります。
標準原価計算との違い
| 原価企画 | 標準原価計算 | |
| 適用領域 | 企画・設計等の計画段階 | 生産段階 |
| 管理目的 | 原価低減・戦略的利益管理 | 原価統制(原価維持) |
| 管理志向 | 市場志向(マーケット・イン) | 技術志向(プロダクト・イン) |
| 管理技法 | 経営工学的な性格 | 会計的な性格 |
| 生産形態 | 多品種少量生産 | 少量大量生産 |
原価改善とは
原価企画で行われた、目標利益を確保する原価の作り込みをとおして、目標原価が設定されます。
それを受けて、次は目標原価に向けて原価改善目標を決定し、その実現を図る原価改善へと進んでいきます。
原価改善
生産段階で行われる原価低減活動を原価改善といいます。
原価改善は、製品や部品の製造原価を改善目標となる原価レベルにまで計画的に引き下げる継続的な活動です。
原価改善は、量産段階に突入した早い時期に新製品の原価目標の未達成部分を埋めてしまおうとする製品別(プロジェクト)原価改善と、既存製品の量産段階で日常的に行う期別(部門別)原価改善に分かれます。
管理手段
1)直接費
製品別にVE、JIT、TQC活動を通じて管理する
2)間接費
予算管理を主として、TQCやTPMを活用して費目別に管理する
原価管理における原価企画の位置付け
原価管理における原価企画の位置付けは以下のとおりです。
| 原価管理 | 原価低減 (=原価の標準自体を引き下げ) | 原価企画 | 製品の開発段階からの総合的利益管理 ・VE |
| 原価改善 | 生産段階における原価低減活動 ・直接費 製品別VE、JIT、TQC活動 ・間接費 予算管理、TQC、TPM | ||
| 原価統制 (=原価の発生を一定の幅に抑える) | 原価維持 | 標準原価の達成(標準原価計算) |
例題
次の文章の( ア )〜( ク )に当てはまる語句および金額の組み合わせとして最も適切なものの番号を一つ選びなさい。なお、( * )に当てはまる語句については各自推定すること。
X社は、コピー・ファックス・プリンタ機能を持つ総合複合機を生産している。最近、技術革新による他国の追い上げによって、価格・品質・納期等の兼ね合いが重要であると認識するようになった。
そこで、X社のトップ・マネジメントは、新製品開発に際し、商品企画から開発終了までの段階で、目標利益を確保するために設定された原価を作り込む活動に取り組むことにした。この活動は( * )と言われる。( * )では、予定販売価格から目標利益を差し引いて( ア )を計算する。次に、原価低減目標額を定めるにあたり( ア )と従来どおりの経営活動で発生すると予想される見積原価である( イ )と擦り合わせて、実現可能な( ウ )を決定する。( ウ )は( ア )と( イ )の間の水準に設定されることになる。このような、( ウ )の設定方法は一般に( エ )とよばれる。例えば、予定販売価格が80,000円/台、目標利益率25%として( イ )が69,000円/台であった場合、それぞれの金額は次のとおりとなる。
・( ア )・・・・・・( オ )円/台
・原価低減目標額・・・・( カ )円/台
この場合、( ウ )は( ア )と一致していることが望ましいが、( ウ )が( ア )を上回る場合、さらにVEなどの活用によって原価低減活動を行なった上で実現可能な( ウ )を決定していく。それでも原価低減目標額が達成未達であれば、その差額分は量産段階における( キ )活動に委ねることになる。ここで決定された( ウ )は、標準化に組み込まれ、( ク )活動に引き継がれる。
解答・解説
ア. 予定販売価格から目標利益を差し引いて計算するので、許容原価になります。
イ. 経営活動で発生すると予想される見積原価を指す成行原価が入ります。
ウ. 許容原価と成行原価をすり合わせて設定するのは目標原価です。
エ. 許容原価と成行原価をすり合わせて目標原価を設定する方法を折衷方式(結合方式)といいます。
オ. 許容原価は予定販売価格から目標利益を差し引いて算定するため、次のように算定されます。
80,000円(予定販売価格)ー(1ー0.25*)= 60,000円
* 目標利益率:25%
カ. 成行原価69,000円に対して、目標利益が60,000円であるため、低減目標額(目標に対していくら下げるか)は9,000円になります。
キ. 生産段階における原価低減活動を原価改善といいます。
ク. 目標原価をもとにした標準原価の維持を原価維持といいます。
X社は、コピー・ファックス・プリンタ機能を持つ総合複合機を生産している。最近、技術革新による他国の追い上げによって、価格・品質・納期等の兼ね合いが重要であると認識するようになった。
そこで、X社のトップ・マネジメントは、新製品開発に際し、商品企画から開発終了までの段階で、目標利益を確保するために設定された原価を作り込む活動に取り組むことにした。この活動は( * )と言われる。( * )では、予定販売価格から目標利益を差し引いて( 許容原価 )を計算する。次に、原価低減目標額を定めるにあたり( 許容原価 )と従来どおりの経営活動で発生すると予想される見積原価である( 成行原価 )と擦り合わせて、実現可能な( 目標原価 )を決定する。( 目標原価 )は( 許容原価 )と( 成行原価 )の間の水準に設定されることになる。このような、( 目標原価 )の設定方法は一般に( 折衷方式 )とよばれる。例えば、予定販売価格が80,000円/台、目標利益率25%として( 成行原価 )が69,000円/台であった場合、それぞれの金額は次のとおりとなる。
・( 許容原価 )・・・( 60,000 )円/台
・原価低減目標額・・・・( 9,000 )円/台
この場合、( 目標原価 )は( 許容原価 )と一致していることが望ましいが、( 目標原価 )が( 許容原価 )を上回る場合、さらにVEなどの活用によって原価低減活動を行なった上で実現可能な( 目標原価 )を決定していく。それでも原価低減目標額が達成未達であれば、その差額分は量産段階における( 原価改善 )活動に委ねることになる。ここで決定された( 目標原価 )は、標準化に組み込まれ、( 原価維持 )活動に引き継がれる。

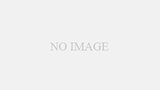
コメント