活動基準原価計算とは
活動基準原価計算(ABC:activity based costing)とは、活動、資源及び原価計算対象の原価と業績を測定する方法論のことで、どの製品やサービスのために発生したのかがわかりにくい間接費を、それぞれの製品やサービスのコストとしてできるだけ正確に配賦することによって、生産や販売活動などのコストを正確に把握しようとする考え方を指します。
従来の伝統的配賦法によれば、直接労務費や直接作業時間などにもとづいて製造間接費を製品に配賦していました。そのため、実際には手間のかかる多品種少量生産には少ない原価しか配賦されず、大量生産品には本来負担すべきでない余分の原価が配賦されてしまい(原価の内部相互補助)、歪んだ製品原価が算定されてしまいます。
昔は少ない種類の製品を大量生産するのが主流のため、直接費の割合が高く、間接費の配賦が不適切でも収益の誤差が目立たない傾向にありましたが、近年の企業環境の変化(多品種少量生産、FA化、CIM化)によって、相関性の薄い生産支援活動(段取、マテハン*等)に関する間接費は増大してきました。
そこで、間接費配賦計算の精緻化目的に、活動基準原価計算(ABC:activity based costing)が登場しました。
* マテリアルハンドリングの略。物流や製造の現場で使われる言葉で、材料や製品などのモノを運搬する作業一般のことをいう。
伝統的配賦法との相違点
伝統的配賦法には次のような特徴があります。
- 原価部門(製造部門と補助部門)を設定し、製造間接費を集計
- 補助部門を製造部門に配賦
- 操業度を基準として製造部門費を製品に配賦
活動基準原価計算(ABC)は次のような特徴があります。
- 活動センター、または活動センターを細分化したコスト・プールを設定する
- 資源作用因(資源ドライバー)に基づいて各間接費を集計
- 活動センター、またはコスト・プールごとの活動作用因(活動ドライバー)に基づいて、間接費を製品に配賦
活動基準原価計算の原価配賦法
ABCでは、「活動が資源を消費し、原価計算対象(製品)が活動を消費する」という基本思考のもと、間接費を活動単位に分割して原価計算を行います。
- 伝統的配賦法における補助部門から製造部門への配賦計算の排除と、それに変わる活動センターとコストプールの設置
- 操業度関連の配賦基準だけではない、活動基準の原価作用因の利用
- 伝統的配賦法に比した計算の精緻化
| 資源 |
| ↓ |
| (資源ドライバー) |
| ↓ |
| 活動 |
| ↓ |
| (活動ドライバー) |
| ↓ |
| 原価計算対象 (製品・サービス) |
製品に関連した活動の区分
製品に関連した活動は以下の4つの階層に分類することができます。
- 以下の順(製品単位レベル〜工場支援レベル)に製品との因果関係は弱くなる
- ABCにおいて、活動を認識する対象は、製品に関する活動期限られない(サービスや販売も可)
製品単位レベルの活動
製品単位レベルでは、活動は1単位の製品が生産されるごとに行われ、これらの活動の原価は生産量と関係しています。例えば、直接工の作業、機械の運転、消費材料、エネルギーの消費などです。これらの原価は、操業度に関連して発生します。
- 材料費
- 直接工の直接労働時間
- 機械運転時間
バッチ・レベルの活動
バッチ・レベルでは、活動はバッチ生産(*1)ごとに行われます。製品の数が多い時に用いられ、例えば、段取り、マテハン(材料、資材の車内移動)、発注処理、品質管理などがあたります。これらの原価は、バッチ処理の回数によって変化します。
*1 1つの品種の、ある程度の量を、まとめて生産する方式
- 段取り回数
- 運搬回数
- 発注回数
- 検査回数
製品支援レベルの活動
製品支援レベルでは、異なるタイプの製品が生産または販売されるごとに活動が行われます。
例えば、製品の仕様書作成、工程管理、技術上の変更、製品機能の強化などがあります。これらの原価を個々の製品に跡付けすることは可能です。しかし、バッチ回数などとは関係なく、仕様書数や工程数で跡付けることになります。
特定の製品を維持するための活動で、以下のようなものが該当します。
- 仕様書数
- 工程数
- 製品数量
工場支援レベルの活動
向上支援レベルでは、活動は工場の生産設備や管理に関連して行われます。
例えば、工場長の仕事、建物の保守、工場の安全対策、工場経理などです。これらの原価は、異なる製品に対して共通して発生するため、特定製品に後付けすることが困難となります。組織全体を維持するものです。
活動基準原価計算の意義
製品の収益性分析や価格決定などの意思決定に有用
ABCは原価計算制度としてよりも、商品戦略を検討するために実施することが多く、製品の正確な収益性が判明し、価格決定に際しても有用な情報を提供します。
原価管理の基礎を提供
ABCは間接費を部門ではなく活動に集約します。そのため、活動に焦点を絞った合理性の追求に有用な情報を提供します。
活動基準原価計算のメリット
活動基準原価計算(ABC)のメリットとして、下記が挙げられます。
(1)より正確な原価を算出できる
製造間接費について正確な原価計算が行えると、より適正な価格設定を行うことが可能となり、利益率の高い製品を明確にできたりなど、事業の推進に役立てることができます。
(2)事業に貢献していない活動を明確にできる
活動基準原価計算(ABC)では、活動単位での原価が明らかになるため、収益と活動を比較することで、今まで見えなかった不採算製品や事業、削減できるものや業務改善に繋げる対象が見えやすくなります。
活動基準原価計算のデメリット
活動基準原価計算(ABC)のデメリットとして、下記が挙げられます。
(1)データの蓄積や整理に時間がかかる
活動単位にデータを蓄積するには、各工程にかかった時間や作業の頻度を知る必要があるため、それらを記録する現場の従業員に負担がかかることになります。
(2)経営判断の材料とするにはリスクがある
活動基準原価計算(ABC)は、あくまで伝統的原価計算と比較して正確な原価が求められるという計算方法です。間接費はそもそも流動的なものも多いため、データを過信して経営判断のような重要な判断に用いるにはリスクが高いと言えます。
例題
当工場では三種類の製品を生産しており、伝統的な製造間接費の配賦計算から活動基準原価計算(ABC)へと変更する場合、製品1単位あたり製造原価がどのように変化するかを調査することにした。次のアからエの記述のうち、正しいものの組み合わせを示す番号を一つ選びなさい。
〔資料〕
1.直接材料費
(1) 直接材料費
製品X:200kg
製品Y:600kg
製品Z:800kg
(2) 材料予定消費単価 240円/kg
(3) 材料は単一であり、購入後、ただちに全て製造工程に投入される。
2.直接労務費
(1) 直接作業時間
製品X:80時間
製品Y:120時間
製品Z:600時間
(2) 予定消費賃率 300円/時間
3.製造間接費
(1) 材料購買関連活動
当月の実際材料購入副費は、購入事務手数料268,800円と材料検査費81,000円であった。購入事務手数料とは、注文処理時間に応じて発生する。1kgあたり予定注文処理時間は製品X、Y、Zそれぞれ、0.6時間、0.2時間、0.4時間である。また、材料検査費は、材料入荷のたびに購入量(材料消費量)に応じて発生する。
(2) 修繕活動
当月の修繕費の実際発生額は84,000円である。修繕費は、修繕回数に応じて発生し、製品X、Y、Zの当月の修繕回数はそれぞれ、4回、6回、10回である。
(3) 段取活動
当月の段取費の実際発生額は63,000円である。段取費は段取回数に応じて発生し、製品X、Y、Zの当月の段取回数はそれぞれ、70回、50回、20回である。
4.生産数量は、製品X500個、製品Y300個、製品Z10,000個である。
5.期中において、販売単価の変更はない
6.伝統的配賦計算では、直接作業時間を配賦基準として採用している。
ア. 製品Xは、配賦計算を伝統的方法からABCに変更した場合の方が、製造単位原価が低い。したがって、ABCによれば製品Xの収益性は高いことがわかる。
イ. 製品Yは、配賦計算を伝統的方法からABCに変更した場合の方が、製造単位原価が高い。
ウ. 製品Yの製造単位原価をABCによって算定すると、1,050.25円である。
エ. 製品Zの製造単位原価は、伝統的配賦計算からABCに変更すると、12.75円減る。
解答・解説
伝統的方法による製品単位原価の計算
| 製品X(500個) | 製品Y(300個) | 製品Z(10,000個) | |
| 直接材料費 | 48,000 | 144,000 | 192,000 |
| 直接労務費 | 24,000 | 36,000 | 180,000 |
| 製造間接費*1 | 49,680 | 74,520 | 372,600 |
| 合計 | 121,680 | 254,520 | 744,600 |
| 製品単位原価 | @243.36 | @848.4 | @74.46 |
*1 購入事務手数料:268,800+材料検査費:81,000+修繕費:84,000+段取費:63,000=496,800
直接作業時間を配賦基準としているため(資料6より)各製品への配賦額は次のようになります。
製品X:496,800×80h/(80h+120h+600h)=49,680
製品Y:496,800×120h/(80h+120h+600h)=74,520
製品Z:496,800×600h/(80h+120h+600h)=372,600
活動基準原価計算による製品単位原価の計算
| 製品X(500個) | 製品Y(300個) | 製品Z(10,000個) | |
| 直接材料費 | 48,000 | 144,000 | 192,000 |
| 直接労務費 | 24,000 | 36,000 | 180,000 |
| 製造間接費 | |||
| 購入事務費 | 57,600(*2) | 57,600 | 153,600 |
| 材料検査費 | 10,125(*3) | 30,375 | 40,500 |
| 修 繕 費 | 16,800(*4) | 25,200 | 42,000 |
| 段 取 活 動 | 31,500(*5) | 22,500 | 9,000 |
| 合計 | 188,025 | 315,675 | 617,100 |
| 製品単位原価 | @376.05 | @1,052.25 | @61.71 |
*2 活動ドライバー(1kgあたりの予定注文処理時間)
製品X:200kg×0.6h=120hr
製品Y:600kg×0.2h=120hr
製品Z:800kg×0.4h=320hr
購入事務費:268,800×120hr/(120hr+120hr+320hr)=57,600
*3 材料検査費:81,000×200kg/(200kg+600kg+800kg)=10,125
*4 修繕費:84,000×4回/(4回+6回+10回)=16,800
*5 段取費:63,000×70回/(70回+50回+20回)=31,500
選択肢について
ア. (誤)製品XはABCに変更した方が、製造単位原価は高いため
イ. (正)
ウ. (誤)1050.25円ではなく、1,052.25円のため
エ. (正)74.46円→61.71円(△12.75円)
よって、イ・エが解答になります。

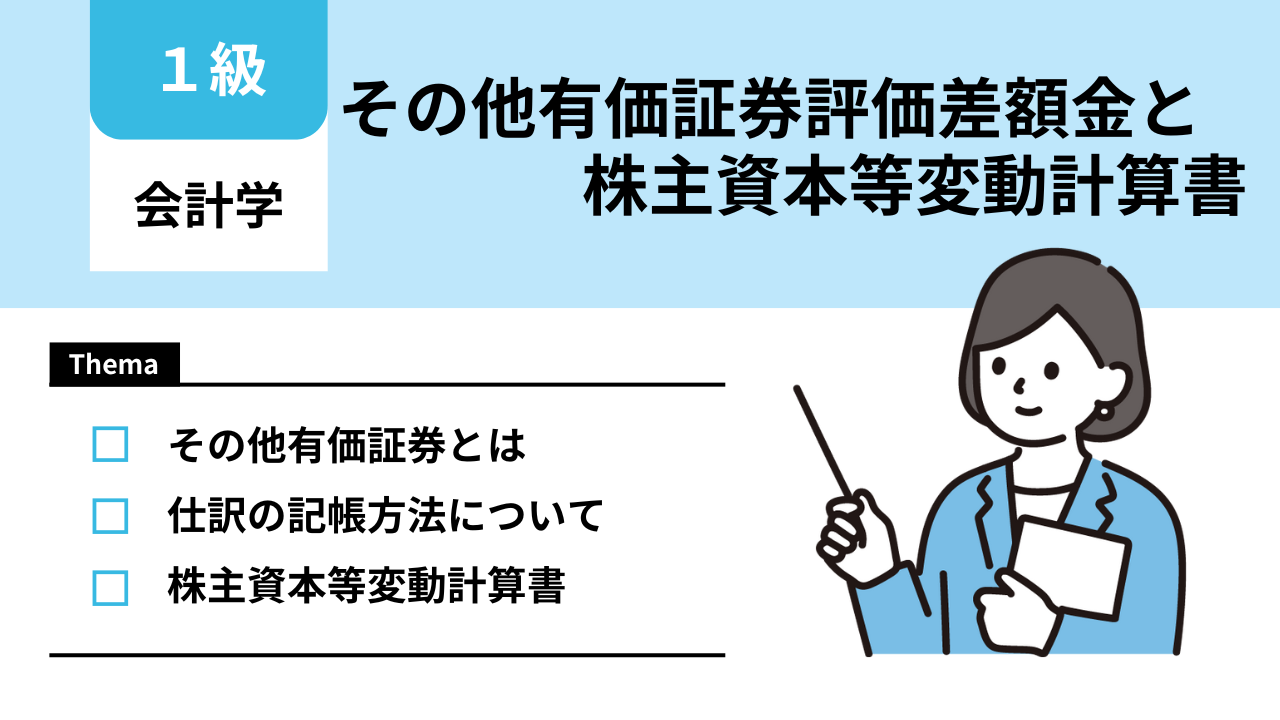
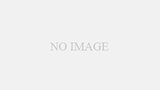
コメント