この記事では、棚卸資産の評価方法について解説します。
棚卸資産とは
商品や製品、半製品、原材料、仕掛品、事務用消耗品などの資産を棚卸資産といい、企業が販売や加工を目的として保有している、商品や製品、原材料、仕掛品などを指します。
棚卸資産は、販売用の商品や製品、未完成の製品、製造のために仕入れた未投入の材料など、将来的に販売を予定しているもののほか、販売を予定していない消耗品も該当します。
棚卸資産の期末評価とは
棚卸資産を保有している企業は、棚卸資産を期末評価する必要があります。
棚卸資産の期末評価とは、決算時に在庫として保有する棚卸資産の帳簿価額を算定することです。棚卸資産の期末評価を行うことによって、その事業年度の売上原価が算定されます。
また、貸借対照表に記載する棚卸資産について適正な評価を行う必要があります。
実地棚卸とは?
期末に棚卸資産の評価額を確定させるためには、期末時点で棚卸資産の数量を明確にする必要があります。商品数がわからないと評価額を計算できないためです。
そこで行われるのが、実地棚卸という作業になります。
棚卸(たなおろし)という言葉どおり、倉庫の棚から在庫を卸して人の手と目を使ってカウントしていく作業のことです。
盗難、紛失、記帳もれなどで帳簿に記載している数量と実際に倉庫に保管されている数量が一致しないケースもあり、棚卸を行って帳簿上の在庫量を実際の在庫量に一致させるために行う非常に重要な作業になります。
棚卸資産の期末評価は売上原価の計算を通して損益計算にも直結します。結果的に納付税額の間違いにつながることも考えられるため、正確な実地棚卸を行う必要があります。
棚卸資産の評価方法
棚卸資産は取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表に記載します。
正味売却価額とは?
資産を売却する際に受け取ることができる金額から、売却にかかる費用を差し引いた純額のことで、その時点において商品が売れる金額を指す
取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理します。
棚卸資産の評価に関する会計基準 第7項
通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産は(中略)期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。この場合において、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理する。
棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は売上原価として処理します。
棚卸資産の製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価として処理します。
| 下記以外の場合(原則) | 売上原価 |
| 製造に関し不可避的に発生すると認められるとき | 製造原価 |
| 臨時の事象に起因し、かつ、多額であるとき | 特別損失 |
また、収益性の低下に基づく簿価切り下げ額が臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには特別損失に計上します。
特別損失に計上する具体的な例としては、重要な事業部門の廃止、災害損失の発生などの限定的なケースがが該当します。
棚卸資産の評価に関する会計基準 第17項
通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下額(中略)は売上原価とするが、棚卸資産の製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価として処理する。また、収益性の低下に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上する。臨時の事象とは、例えば次のような事象をいう。なお、この場合には、洗替え法を適用していても(第14項参照)、当該簿価切下額の戻入れを行ってはならない。
(1) 重要な事業部門の廃止
(2) 災害損失の発生
棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、取得原価を持って貸借対照表価額とする方法(原価法)と、時価が取得価額よりも下落した場合には時価を持って評価する方法(低価法)に分かれています。
原価法とは
原価法は、棚卸資産の取得原価をもとに棚卸資産を評価する方法です。
原則は原価のまま評価を据え置きますが、棚卸資産の収益性の下落によって正味売却価格が取得原価を下回ったときに限り、回収可能額を貸借対照表上に反映させるために正味売却価格まで帳簿価額を切り下げます。
原価法による取得価額の求め方には、次の6つの評価方法があります。
| 原価法 | 個別法 | それぞれの商品について仕入時の価格で評価する方法です。 個別の売上と原価が完全に一致し、正確な評価ができる一方で、商品を実際の仕入・払出の通りに計算するので数や種類が多い場合は手間がかかります。 |
| 先入先出法 | 先に仕入れた棚卸資産から順に売り出し、あとから仕入れた棚卸資産が期末に残ると考えて計算する方法です。 実際の資産の流れに近い状態で計算できますが、極端な物価変動があった場合、インフレ時には利益が多く評価され、デフレ時には小さく評価されてしまいます。 | |
| 総平均法 | 棚卸資産の平均取仕入単価を原価とする方法です。期末になるまで商品単価は計算できません。 | |
| 移動平均法 | 仕入れごとにその時点の在庫と仕入金額から棚卸資産の平均単価をその都度計算する方法です。 常に現状を把握できますが、商品の仕入の都度計算するため単価の計算が煩雑になります。 | |
| 売価還元法 | 種類の近い商品をグループとして、期末時点の棚卸資産の販売価額の合計額に、原価率をかけて計算した金額で評価する方法です。 | |
| 最終仕入原価法 | 期末に最も近い時期に仕入れ際の価格を、当期の取得価格として計算する方法です。単純で分かりやすく、計算もしやすい反面、物価変動を受けやすいだけでなく、期末まで原価を特定できない点もデメリットです。 |
低価法とは
低価法は、原価法を使って評価した棚卸資産の評価額と、期末時点の時価による棚卸資産の評価額を比較して、低いほうを棚卸資産の評価額とします。
| 低価法 | 原価法のいずれかの方法で出た帳簿価額と期末時点での時価と比較して評価額が低い方を採用する方法です。 低価法には翌期首において評価損に相当する金額の戻入れ益を計上する「洗替低価法」と戻入れ益を計上しない「切放し低価法」がありますが、税務上は平成23年4月1日以後に開始した事業年度から「切放し低価法」は廃止されています。 |
低価法には、次のようなメリットがあります。
- 棚卸資産の評価額が実態に即したものになる
- 収益性の低下が早期に認識できる
- 節税効果がある

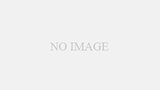
コメント