この記事では売価還元法の計算方法について解説します。
(この記事にはアフィリエイトリンクが含まれます)
売価還元法とは
棚卸資産を適切に評価するために毎期末どのくらい在庫があるか、価格の下落が生じていないかといったことを確認する必要があります。
しかし、多様な品目を扱う小売業や卸売業などでは多くの手間と時間がかかります。そこで、取り扱う品目の多い小売業や卸売業を中心に活用されているのが売価還元法です。
売価還元法とは、棚卸資産の評価方法の一つで、棚卸資産のグループごとの期末の売価合計額に原価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資産の価額とする方法をいいます。
売価還元法は主に、数多くの商品を取り扱う小売業(百貨店やスーパーマーケットなど)や棚卸業(メーカーと小売業の中間に位置する)を中心に活用される方法です。
原価率は仕入れた全ての商品(期首商品を含む)が売価(値札)どおりに売却されたと仮定したときの、原価と売価の平均的な比率といえます。
また、売価還元法では種類の近い商品をグループとして(法人税基本通達5-2-5)、期末時点の棚卸資産の販売価額の合計額に原価率をかけて計算した金額で評価します。
売価還元法による評価方法
原価率の計算
原価率は、仕入原価 ÷ 販売格価 で計算できます。
また、原価率は事業年度を通じたものである必要があるため、次のようなデータをもとに計算します。
(A商品グループに関するデータ)
| 仕入原価 | 販売価格 | |
| 期 首 商 品 | 100 | 150 |
| 当期仕入高 | 600 | |
| 原始値入額 | 200 | |
| 値 上 額 | 90 | |
| 値上取消額 | ▲30 | |
| 値 下 額 | ▲20 | |
| 値下取消額 | 10 | |
| 売 上 高 | 800 |
仕入原価:100+600=700
販売価格:150+600+200+90ー30ー20+10=1,000
700 ÷1,000=0.7
よって、原価率は 70%となります。
期末商品の評価
期末棚卸資産の売価に原価率をかけて棚卸資産の期末評価額を計算します。期末商品の売価は、期首商品と当期仕入高の売価から、当期の売上高を差し引いた額になります。
1,000(上記の販売価格計)ー 800(売上高)= 200(期末商品帳簿価額(売価))
よって、期末商品棚卸高(原価)は
200×70% =140となります。
このように、売価還元法は原価率に基づいて期末商品を評価する方法になります。
例題
例題を通して、下記のポイントを押さえましょう。
- 原価率の計算
- 棚卸減耗損と商品評価損の計算
以下の資料をもとに、(1)(2)それぞれの場合におけるア. 棚卸減耗損、イ. 商品評価損、ウ. 貸借対照表に計上される商品の金額を計算しなさい。なお、棚卸資産の評価に関しては売価還元平均原価法を採用している。
〔資料〕
- 期首商品棚卸高(原価):54,600千円
- 期首商品棚卸高(売価):72,800千円
- 当期商品仕入高:354,900千円
- 原始値入額:133,460千円
- 期中値上:49,150千円
- 期中値下高:31,480千円
- 期中値上取消額:28,720千円
- 期中値下取消額:18,640千円
- 期末商品実地棚卸高:66,000千円
- 期末商品正味売却価額:42,000千円
- 当期売上高:500,000千円
原価率の計算
期首商品(原価)と当期仕入高(原価)の合計に対する売価の比率を原価率とします。
仕入原価:54,600+354,900=409,500
販売価格:72,800+354,900+133,460+(49,150ー28,720)ー(31,480+18,640)=568,750
409,500÷568,750=72%(原価率)
棚卸減耗損の計算
棚卸減耗損(費用勘定)とは、期中に発生した商品の紛失や破損等により、実際の棚卸資産が帳簿価額より減っているときに計上する損失のことです。
売価還元法では、棚卸減耗損も売価ベースで計算します。
| 原価率 72% | ||||||
| 棚卸減耗損 1,980 | ||||||
| あ | 66,000(実地) | 68,750(帳簿)* | ||||
* 原価率の算定で求めた販売価格 ー 売上高 = 期末商品帳簿価額(売価)
568,750ー500,000=68,750千円
商品評価損
期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とします。また、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用(商品評価損)として処理します。
期末商品実地棚卸高(原価)は47,520千円(66,000×72%)であるのに対して、正味売却価額は42,000千円であるため、商品評価損として簿価を切り下げます。
| 原価率 72% | ||||||
| 商品評価損 5,520 *3 | 棚卸減耗損 1,980 *2 | |||||
| 商品(貸借対照表) 42,000(ウ) | ||||||
| あ | 66,000(実地) | 68,750(帳簿) | ||||
*1 68,750ー2,750=66,000 期末商品実地棚卸高(売価)
*2 2,750×72%=1,980(ア)
*3 66,000×72%ー42,000=5,520(イ)

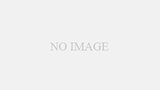
コメント